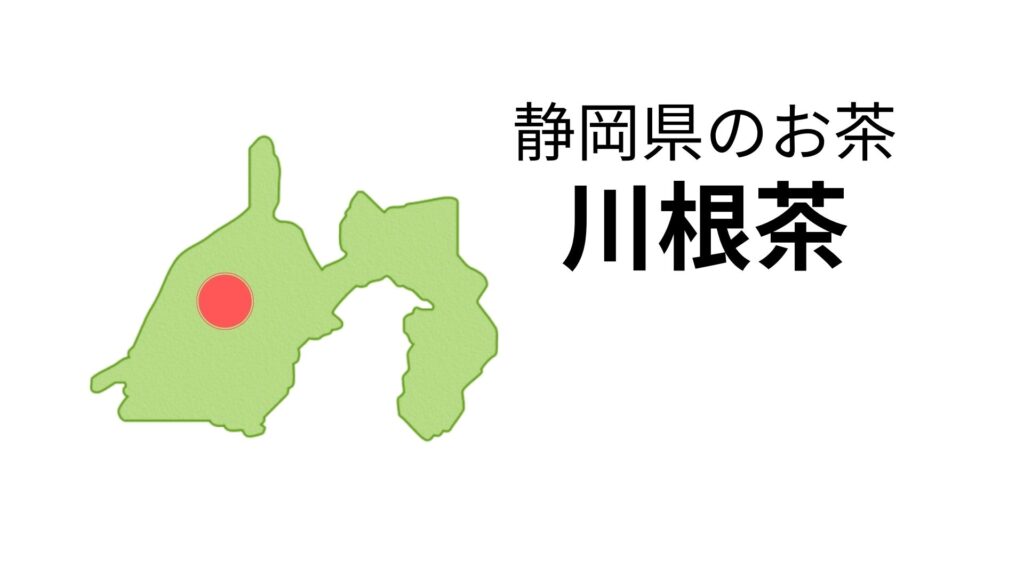
静岡県の中部、大井川の上流域で生産されている川根茶(かわねちゃ)。日本屈指の茶の産地として知られる静岡でも、太平洋側に位置する南部に比べて昼夜の寒暖差が大きいこの地域。特に大井川近辺では、発生する川霧の影響で日照時間が短く、茶葉に味や香りが凝縮されている。仕上げは静岡茶の「深蒸し煎茶」ではなく「普通蒸し煎茶」が一般的で、全国の品評会でも多数の賞を取っているほど、品質には定評のある銘柄である。
製法・味
川根茶は静岡茶で一般的な「深蒸し」ではなく、「普通蒸し」で煎茶が仕上げられています。(一部では「普通蒸し」ではなく「浅蒸し」とも表現されています。)
普通蒸し煎茶は、茶葉の特徴や影響をそのまま受けやすいのが特徴です。一般的には深蒸しに比べて香りが強く、鮮やかな緑色をします。反面、深蒸し茶に比べて茶葉の渋味が出やすく何度もお湯を入れて飲むことが出来ません。
ここ川根茶の茶葉は後述の通り品質の高いものが採れやすく、旨味が多く香り高い茶葉が特徴です。つまり川根茶の普通蒸しは、例えて言うなら品質の良いイチゴを何も付けずにそのまま食べているような感じです。
産地
お茶の名産地である静岡県で南北に流れる川、大井川の上流地域で生産されている川根茶。南アルプスにも近い山間部で栽培されています。
太平洋側から流れてくる暖かい空気と、南アルプスから流れてくる冷たく湿った空気により昼夜の寒暖差が大きいこの地域。さらに湿った空気が大井川の川霧や山霧を発生させ、日照時間を短くさせます。これらの気象環境により、茶葉に栄養が蓄えられやすく、苦味が少なく旨味が多い茶葉に仕上がるのです。
歴史
記録として残っている限りでは、川根茶の始まりは今から約400年前の江戸時代あたり。この地域で茶が年貢(税金)として収められていたり、販売されていた記録が残っています。茶の栽培が普及するまでには時間がかかるため、実際にはもう少し前に茶の栽培などが伝わっていたのかもしれません。
明治時代にかけて、海外でもその品質が評価され、輸出も盛んに行われていきました。作れば売れる時代ということもあり、生産量も増加していきます。また現在主流となっている品種「やぶきた」の導入が早かったこともあり、安定して量産できる産地となっていきました。
現在では全国の品評会でも常連の高級な銘柄としての地位を確立しています。しかし、全国的に茶の生産量は減少傾向で、川根茶も同じく下がってきています。それでも高い品質と知られている銘柄ということもあり、他の地域に比べればその減少幅は小さく、ほぼ横ばいで推移しています。
品種
川根茶の大部分は全国的にも一般的な「やぶきた」品種です。しかし近年では早生品種である「山の息吹」、晩生(おくて)品種である「おくみどり」の生産が盛んに行われています。
コメントを残す